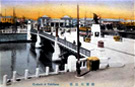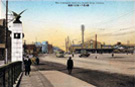|
|
第7号 2006年11月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ごあいさつ 19世紀の西洋人は、自分たちに世界を文明化する義務があるという尊大な考えをもっていました。19世紀の文明とは端的に科学・機械文明のことであり、とくに鉄道は文明化の牽引車と考えられていました。日本を開国に導いたアメリカのペリー提督も、自らの使命を「特異で半ば野蛮な一国民を、文明諸国民の家族の中に組み入れる」ことだと明言しています。そのペリー提督が、日本への贈り物のなかに模型の蒸気車と電信機を含めたのは、文明の威力を見せつけるためでした。 日本人は西洋人の尊大さに時として反発しつつも、科学・機械文明の価値にはほとんど疑いを抱きませんでした。京浜間に鉄道が開通したのは、ペリー提督が模型の蒸気車を披露した1854年から数えてわずか18年後の明治5(1872)年のことでした。 中国最初の鉄道が上海―呉淞(ウースン)間に開通したのは、それより遅い1876年、しかもそれはイギリス商人たちが中国政府に無断で建設したものでした。政府の手になる鉄道の開通は1881年ですが、これはラバが牽(ひ)くもので、蒸気機関車が導入されたのは翌年、中国が南京条約によって西洋諸国に門戸を開いた1842年から数えて40年後のことでした。 西洋文明の窓口である横浜と結ぶ東京側の駅が、築地の外国人居留地の西に接する新橋に設けられたように、それは強く西洋諸国の目を意識したもので、折しも焼失した隣接の京橋地区に銀座煉瓦街が建設されたことと軌を一にするものでした。 明治5(1872)年9月12日の開業式当日、昨日までの荒天が嘘のような晴天のもと、明治天皇が乗車して新橋―横浜間を往復する間、両駅では花火が打ち上げられ、横浜の町は日章旗と日の丸を描いた提灯で飾られました。これが国旗掲揚の最初とされます。東京では軽気球を飛ばす計画もあったのですが、それが実施されたかどうか、まだ確認していません。いずれにせよ、それは単なる鉄道開通というよりも、“文明国家建設宣言”ともいうべき、国を挙げての祭典だったのです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄道と横浜 ―横浜駅をめぐる明治・大正・昭和― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜は幕末に貿易港が開かれ、都市としての歴史が始まった。横浜のまちと海上交通との関わりの深さについては改めて述べるまでもない。 では、かつて「陸上交通の王者」と呼ばれた鉄道と、横浜のまちはどのように関わってきたのだろうか。横浜駅はその場所を三つも変えた全国でも珍しい駅である。 本特集では「鉄道の日」(10月14日)にあわせて、横浜駅をめぐる鉄道と横浜の歴史について概観してみよう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道の創業と横浜駅 (第1図参照) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1図 初代横浜駅と鉄道網 縮尺約6万分1、『港町・横浜の都市形成史』(横浜市、1981年)挿図に加筆。以下同。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1872(明治5)年10月14日(旧暦9月12日)、日本で最初の鉄道が東京の新橋から横浜まで開通した。当時の横浜駅は、現在と異なり、いまの桜木町駅であった。その立地は、東京から来た線路が横浜のまちに突き当たる位置で、開港場の周縁部であった。 さて、明治政府にとって、東京と大阪を鉄道で結ぶことは重要な課題であり、当初そのルートは中山道沿いに考えられていた。つまり、東京から北上して高崎、信州を経由して西へ向かうのである。先にできた京浜間の鉄道は、その支線として位置づけられていた。 ところが、中山道ルートは山岳地帯を走るため工事が難しく、結局、1886(明治19)年に東海道まわりのルートに変更されることが決定した。そのため、京浜間にすでにある鉄道を活かし、横浜から線路を西へ伸ばすことになった。87(同20)年に国府津までが完成し、89(同22)年、新橋―神戸間に東海道本線が全通した。 東海道本線のルートは、横浜駅で全ての列車が方向転換(スイッチバック)をしなければならないものとなった。これは、もともと横浜駅が線路を西へ伸ばすことを前提に設置されていなかったことと、そもそも横浜というまちが東海道から外れていたからこそ開港場として選ばれた経緯に起因する。 だが、1894(明治27)年、日清戦争が勃発し、鉄道での軍事輸送が必要となると、軍は横浜駅での方向転換の不便を解消するため、神奈川と保土ヶ谷の間に横浜駅を通らない短絡線を設けさせた。これはあくまで戦時の特別輸送用だったが、やがてこれを普段の旅客線用として使う計画が起こる。東海道の交通から横浜が外れることになるため、横浜市側は国に激しく抗議をするものの、結局、この短絡線が本線となった。その線上に平沼駅を設けて横浜市民の便宜ははかったが、当時としては横浜の市街地から全く離れていた。 横浜駅への支線を走るのはローカル列車と貨物列車だけとなってしまったのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海道本線の改良と横浜駅の変転 (第2図参照) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2図 第2代横浜駅と鉄道網 緑線は貨物線のルート、白文字は貨物駅の名称を示す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大正時代になると、東海道本線の輸送量は増大し、旅客用と貨物用の線路の分離が進められた。その改良工事の中で横浜駅の移転も行われることになった。1915(大正4)年、平沼駅が廃止され、東海道本線の線路を横浜の市街地寄りへ迂回するルートに移し、高島町に新しく2代目の横浜駅がつくられた。これは旅客専用の駅である。埋立地の表高島町に高島貨物駅を別に設けて、こちらを東海道本線の貨物専用ターミナルとした。 一方、初代の横浜駅は、旅客駅の桜木町駅と貨物駅の東横浜駅に分離・改称された。さらに東横浜貨物駅から新港ふ頭まで新たに貨物線が建設され、ふ頭内に横浜港駅が設置された。ここでは貨物列車だけでなく、「ポートトレイン」と呼ばれる港湾連絡用の旅客列車も臨時に発着した。なお、これらの線路の跡が今日、遊歩道化されて「汽車道」となっている。 また、2代目横浜駅の開業にあわせて、東京―横浜―桜木町に省線電車(後の国電)が走るようになった。明治時代に鉄道といえば、蒸気機関車が客車を引くいわゆる「汽車」のことで、「電車」とは道路上の軌道を走る路面電車を指していたが、この頃より、汽車と同じ専用の線路を走る高速の電車が登場したのである。 しかし、1923(大正12)年に起きた関東大震災により、横浜駅も 桜木町駅も完全に倒壊してしまう。震災からの復興が急務となり、これを機会に横浜でも新しい都市計画、交通計画が進められるが、鉄道省は東海道本線のルートの改良を再度はかる。横浜駅付近で線路が迂回しているのを再び直線化、2代目横浜駅と桜木町駅を廃止して平沼駅跡に新しい横浜駅を設けようとしたのである。 横浜市は桜木町駅の廃止に強く反対し、最終的に東海道本線は移設するが、桜木町ヘの支線は存続させ、新しい横浜駅はこの両線の分岐点に置くということになった。これが現在の横浜駅で、1928(昭和3)年開業の3代目である。 なお、神奈川駅はこの新しい横浜駅と近くなりすぎるため廃止されることになった。「横浜」駅がますます「神奈川」に接近したのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜駅周辺の繁華街化と戦後の都市横浜 (第3図参照) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3図 第3代横浜駅と鉄道網 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3代目横浜駅の特徴は多くの私鉄が集中して乗り入れたことである。1928(昭和3)年に東京横浜電鉄(現・東京急行電鉄)、30(同5)年には京浜電鉄(現・京浜急行電鉄)、そして33(同8)年には神中鉄道(現・相模鉄道)という順である。 それでも戦後しばらくまでは、乗り換え客が中心で、駅の周辺には工場や倉庫、資材置き場などが広がっていた が、昭和30年代に入ると、相模鉄道によって駅西口の商業地としての開発が始まる。まず「相鉄名品街」(現・相鉄ジョイナス)をオープンし、高島屋を誘致してターミナルデパートを誕生させ、映画館や劇場をつくっていった。それに連動して国鉄の西口駅舎がステーションビルに生まれ変わり、地下街もできていく。横浜駅周辺が繁華街として急速に成長し、横浜の中心商店街であった伊勢佐木町のにぎわいをしのぐようになっていったのである。 一方、1964(昭和39)年、桜木町で終点となっていた国鉄の線路が延長され、根岸線が開通した。横浜の旧来の中心部を初めて鉄道が貫通し、関内駅が開業した。これで関内地区や伊勢佐木町への交通アクセスが改善されるが、横浜駅の巨大化と駅周辺の成長はとまらなかった。 やがて横浜の都心は、商業中心地である駅周辺地区と、行政・業務中枢機能の残る関内地区との二極に分離していく。 横浜のまちと港は、東海道の神奈川の宿場を離れた場所に成立した。だが、港を中心に形成された横浜のまちの構造を大きく変えていったのが、「ミナトまち」という横浜のイメージとはうらはらに、実は鉄道だった。 紆余曲折の末、神奈川方面に移動していった鉄道のターミナル横浜駅は、かつての「神奈川」に新しい「横浜」を生み出したのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (岡田 直) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハマの土管、海を渡る ―仁川広域市立博物館を訪ねて― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海を渡った土管 この夏、当館の所蔵資料がはじめて海外の博物館で紹介される機会に恵まれた。 海外デビューの舞台となったのは、韓国の仁川(インチョン)広域市立博物館で開催された特別展「都市紀行―上海・横浜・仁川」(2006年7月10日〜9月10日)である。同館からの出品依頼を受け、明治期の土管や鉄道レールなど、近年の地下遺構調査で出土した遺物類が海を渡っていった。また横浜開港資料館からも、石版画「ペリー横浜上陸図」をはじめ、居留地境界石などの貴重な資料が多数出品された。 同館からはあわせて開幕式典への招待も受け、当館および開港資料館では、高村直助館長(両館兼任)と2名の調査研究員が仁川を訪問し、特別展のオープニングに同席することとなった。当館にとって、開館以来はじめての国際交流の機会である今回の韓国訪問について、この場を借りて報告したい。 韓国の開港場・仁川 ソウルの西およそ30kmに位置する仁川は、国際空港のある韓国の空の玄関として知られているが、横浜と同じく、開港をきっかけに近代都市として急成長を遂げた港湾都市である。 仁川が開港したのは1883年のこと。1876年に締結された日朝修好条規で、釜山のほか二港の開港が定められたが、済物浦(チェムルボ)と呼ばれる小さな港だった仁川は、首都漢城(現在のソウル)への玄関口としての重要性から、釜山(1876年)、元山(1880年)に続いて、1883年1月に開港した。 開港後の仁川では、日本専管居留地が設定され、それを取り囲むように清国の専管租界や各国の共同租界が設けられた。領事館や税関の建設とともに市街地が造成され、沿岸部では港湾施設の整備がおこなわれた。背後の丘陵地には韓国最初の洋風公園(現在の自由公園)も開園し、やがて居留地には洋風建築が建ち並ぶ街並みが出現した。 こうした一連の都市形成の過程からは、横浜と多くの共通項を見いだせる。むろん、その後の両都市の歴史を考えれば、都市構造や都市施設という類似点のみを取り上げて、似ていると結論づけられるほど単純な話でないことは言うまでもない。その意味で、上海を含めた三都市を比較対象とする今回の特別展は、東アジアの開港場というより大きな視野のもと、各都市を位置づける試みであったといえる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
都市紀行―上海・横浜・仁川 仁川広域市立博物館は、第二次世界大戦後まもない1946年4月に設立された、韓国でもっとも古い歴史をもつ公立博物館である。原始・古代から近代にいたる仁川市域の歴史を取り扱った総合博物館で、今年が開館60年の節目にあたることから、博物館の増築と常設展示のリニューアル、そして特別展「都市紀行―上海・横浜・仁川」が企画された。 オープン当日には、開館60周年を祝う式典がおこなわれ、その様子は地元のテレビ・新聞でも大きく取り上げられた。特別展も好評で、4万人を超える来場者を記録したという。 特別展は、上海、横浜、仁川という東アジアの三つの開港場をとりあげ、その都市形成の歴史を比較するものであった。展示は九つのコーナーから構成され、開港前の都市風景、開港過程、租界の形成と拡大、近代建築と都市風景、都市の基盤施設、商工業と貿易都市への発展、近代文物の伝来と都市の変化、都市の外国人、都市の試練と再生、とテーマごとに三都市の資料が並列して展示されていた。古写真や絵葉書、地図などの画像資料が大きな壁面に散りばめられ、非常に華やかな展示空間であった。 当館からの出品資料は、いずれも昨年の企画展「地中に眠る都市の記憶」で紹介した近代の出土遺物で、鉄道開 業時の双頭レールと徳利(第二代横浜駅跡地出土)、居留地の下水道に用いられていた土管と枕木(日本大通り出土)である。 これらは都市基盤の整備を扱ったコーナーで紹介されていたが、意外にも仁川側の資料は、郵便ポストや電球、碍子など比 較的新しい時代のものが多かった。学芸員によると、仁川では近代の遺物はなかなかないのだという。その状況は横浜でも同じである。近代遺跡と言ってみても、調査の機会さえつかめない場合が多いのだから。 今後は、仁川でも積極的に近代遺跡に目を向けたいとのことである。そのときには、当館で進めている近代遺構・遺物調査の成果が、きっと有用な資料となってくれることであろう。開港場という両都市の共通点を端緒としてお互いの研究が深まることを歓迎したい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
活用がすすむ仁川の近代建築 さて今回の訪問では、わずか一日ではあるが、戦前の近代建築が残る仁川市内の旧居留地を見学することができた。 仁川は朝鮮戦争のときに連合軍の上陸作戦の舞台となったため、市街地の大部分は破壊を受けている。しかし現在でも、旧日本領事館(現・中区庁舎)をはじめ、仁川郵便局、旧第一銀行仁川支店など、市内各所に戦前の近代建築が残っている。 その中のひとつ、旧第十八銀行仁川支店を訪問した。現在、近代建築博物館として整備中とのことで、工事中の館内を特別に拝見させていただいたが、展示室には床面いっぱいに仁川の地図が広がり、近代建築の模型やCG映像、情報端末つきの居留地ジオラマ模型など、ヴィジュアル重視の展示手法が駆使されていた。また建物そのものを歴史資料として捉え、壁面をガラス貼りにして、当時の煉瓦壁を見せる箇所もあった。これは、日本の歴史的建造物の活用でもよく見られる手法である。 しかし、ひとつの都市の歴史を近代建築という切り口で紹介する博物館は、日本ではほとんど例がない。それだけに、現在の仁川の街づくりにおいて、近代建築の活用がハード・ソフトの両面でいかに重視されているかを感じさせられた。建築専門の博物館としてユニークな存在となるであろう。 一方で、旧居留地内には、上記のような文化財クラスの建築以外にも、古びた小規模店舗がそこかしこに残っている。こうした無名の歴史的建造物群も含めて歴史的環境をどのように継承していくかが、今後、議論の焦点となっ ていくのではないか。 現在、仁川では急速に都市開発が進んでおり、臨海部の様相はさながら横浜のみなとみらい地区を彷彿とさせ る。そのなかにあって、過去の歴史遺産をどのように現在の都市の豊かさとして取り込んでいくのか。都市仁川の未来像に期待するものは 大きい。 最後に、このたびの訪問では、仁川広域市立博物館の尹龍九氏、裴晟洙氏、李羲仁氏をはじめ、多くの方々から熱い歓迎を受けた。この場を借りて御礼申し上げるとともに、特別展の成功を心からお祝い申し上げたい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| (青木 祐介) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
−常設展示より− 横浜の歴史とともに歩む 桜木町駅物語 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
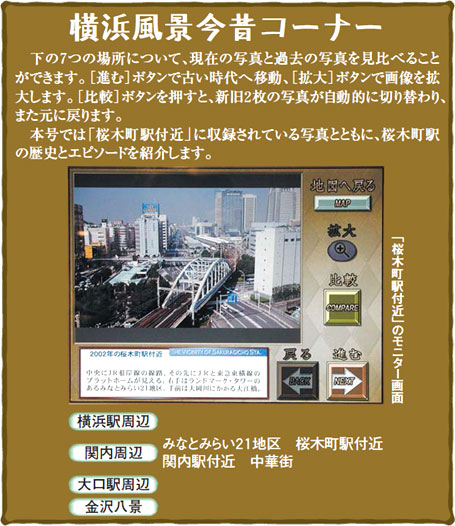 昭和39年に根岸線ができるまで、桜木町駅は横浜の都心に一番近い駅であった。桜木町経由、市電や市バスを使って通勤・通学するのは当たり前のことだった。だから駅前ではいろいろな行き先のいろいろなバスがひっきりなしに発着していた。 子どもの頃、「野庭口行き」ってなんて読むんだろう、「のにわぐち」か「やばこう」か(正しくは「のばぐち」)、どんなところなんだろう、と頭をひねりながらバスを眺めているのは楽しいことだった。成人してから自分が野庭団地に住むことになろうとは思いもよらず、またこの駅が日本最古で、ここが鉄道発祥の地だとも知らず。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
桜木町駅が最初の横浜駅 桜木町駅の地は、開港前は海苔ひびの連なる海だった。京浜間に鉄道を敷設するということでにわかに埋立が進み、明治5年9月ここに駅舎が完成、12日には盛大に開業式が挙行された。 アメリカ人建築家ブリジェンスによって東京の新橋駅と同じデザインで設計された初代横浜駅は、文明開化を象徴する建物の一つだった。大正4年高島町に2代目横浜駅が完成し、横浜駅としての地位と名称を失って、桜木町駅といういかにもローカルな名称に変わりながらも、横浜市民にとっては重要性を失うことなく、大正12年の関東大震災で倒壊するまで、半世紀にわたって働き続けた駅舎だった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2代目桜木町駅舎 震災後、多くの公共施設が最新の鉄筋コンクリート工法で再建され、震災前に勝るとも劣らない威容を誇ったのに対して、昭和2年に再建された桜木町駅舎は木造モルタル塗りであった。昭和20年の横浜大空襲で周囲が焼け野原となりながら、駅舎は奇跡的に焼失を免れた。平成元年市制百周年を記念して開催された横浜博覧会の開幕に合わせて、新駅舎を開設するために解体されるまで、じつに約60年間働き続けたのである。先代に劣らぬ働き者であった。 お世辞にも立派とはいえないこの駅舎は、かえって戦後のこの地域の雰囲気になじんでいたともいえる。西側の野毛地区には露天商が密集し、東側の新港埠頭では多数の港湾労働者が働いていた。夕暮れ時、大岡川河畔、大江橋際の酒屋の前で、一杯やりながら疲れを癒す港湾労働者の黒山のような人だかりも忘れられない光景である。 幻に終わった桜木町民衆駅構想 昭和20年代後半から30年代にかけて、戦後復興が徐々に軌道に乗り、市内は活気を取り戻しつつあった。33年の開港百年祭に向けて、新市庁舎の建設や横浜市史の編纂が進められた。符節を合わせるかのように、桜木町民衆駅構想が浮上したのは26年、30年から32年にかけて本格化した。 民衆駅というのは、国鉄が地元の資金協力を得て駅舎を建設し、商業施設を併設することによって利益を地元に還元するというアイディアである。桜木町民衆駅構想は、戦災をかいくぐり、健気に働き続けているとはいえ、いかにもみすぼらしい駅舎をこの手法で蘇らせ、あわせて周辺商業地区の活性化を図ろうという計画であった。しかし国鉄側の反応は鈍く、30年に十河(そごう)信二新総裁が就任してからようやく前向きに検討が開始され、32年には構想も具体化して許可を待つばかりとなった。 桜木町駅設立準備委員会が立案した構想は、地下2階・地上8階建、延床面積約1万坪、総工費15億円、地下は機械室、1・2階を国鉄に無償で提供し、7階までは商業施設、8階には音楽・演劇ホール、屋上にはヘリポートを設け、さらに野毛山方面に向けて空中ケーブルカーを設置するという壮大なものであった。 32年9月中には国鉄民衆駅審議会で許可が出るものとばかり思われていたのだが、意外にも期待は外れてしまった。なぜか許可が下りなかったのである。残念ながら野毛山にロープウェイを架け渡すという斬新なアイディアも夢と消えてしまった。(以上、『神奈川新聞』昭和30年7月17日号及び32年8月7日号による。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
現在の桜木町駅 現在、桜木町駅周辺では、地上を根岸線の高架が走り、地下には高速道路の神奈川1号横羽線と市営地下鉄が走る多重立体交差が行われている。この地が交通上のキー・ポイントであることは昔と変わらない。 東側には貨物駅の東横浜駅と三菱重工業横浜造船所の跡地を再開発した最新市街のみなとみらい地区が広がり、西側は大道芸や大衆芸能を“売り”にユニークな街づくりを進める野毛地区と「野毛ちかみち」という地下道で結ばれている。相変わらず賑やかな駅ではあるけれども、ガード下に改札口や事務所があるだけの、駅舎の態をなさない現在の桜木町駅は、初代横浜駅の歴史を知り、2代目桜木町駅舎に郷愁を抱く者にとっては少しさびしい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| (斎藤多喜夫) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [寄贈資料の紹介] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年4月以降に新しく寄贈していただいた資料です。(敬称略)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集後記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本号は10月14日の「鉄道の日」にあわせて誌面を構成いたしました。ほとんどの人が「ヨコハマ」と聞いてイメージするのは、「ミナト」や「船」かもしれませんが、実は横浜は日本の鉄道発祥の地でもあります。桜木町駅の駅前にはそれを記念する碑があり、また、駅の構内には写真パネルも展示されています。上記の記念展示とあわせてご観覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||