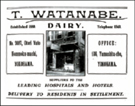|
|
第5号 2005年10月
|
|||||||||||||||||||||
|
ごあいさつ 20世紀は「戦争と革命の世紀」と呼ばれることがあります。この言葉ですぐに思い起こされるのは二度の世界大戦でしょう。その結果、世界中で多くの都市が破壊されました。日本でも第二次大戦の末期、横浜を含め、多くの都市が焼け野原となりました。東京と横浜は大正12(1923)年の関東大震災でも壊滅的な打撃を受けています。 「遺跡」を辞書で引いてみると、「貝塚・古墳・集落跡など、過去の人類の生活・活動のあと」と記されています。都市を巨大な集落と考えると、横浜のように二度も破壊された都市の場合、再建された都市の地下はすべて遺跡だと言っても過言ではありません。 また、「遺構」を引いてみると、「昔の都市や建造物の形や構造を知るための手がかりとなる残存物」と記されています。一昨年は関東大震災から80 年目に当たりましたが、震災復興期に建てられ、戦災にも耐えた建造物がこの十数年間に老朽化して建て替えられました。建て替えをともなう再開発や道路・公園の整備工事などに際して、震災前の遺構がしばしば発見されています。 当館の設立準備の過程はちょうどその時期に重なっており、平成13(2001)年県庁前の日本大通り地下から発見された明治時代の下水道マンホールの模型や、その際剥ぎ取った道路の断面、翌年本町小学校の校庭から出土した日本最古のガス管などは、当館常設展示の「目玉」となっています。 開館後も一昨年の二代目横浜駅やフランス領事館など、遺構の発見が相次ぎました。9月3日から開催中の企画展示「地中に眠る都市の記憶―地下遺構が語る明治・大正の横浜―」は、地下遺構にスポットライトを当てるものです。終戦から60年目に当たる今年、震災や戦災で破壊された都市の地下に眠る先人たちの生活の痕跡に思いを馳せるのも、意味のあることではないでしょうか。 |
|||||||||||||||||||||
地中に眠る都市の記憶 ―地下遺構からのメッセージ― |
||||||||||||||||||||||
|
発見が相次ぐ居留地建築 横浜の都市形成史を語るうえで、1923(大正12年)の関東大震災は、その後の都市景観を一変させた最大の転換点にあたる。赤煉瓦(れんが)の建築に彩られた華やかなりし明治・大正の都市の姿は、マグニチュード7・9の激震によって、一日にして壊滅した。 しかし、思わぬところから震災前の建造物が発見されることがある。現在の山下町一帯にあたる旧山下居留地の例で言えば、旧48番館の建物の一部および旧91番地の塀が発見され、文化財指定を受けたことは記憶に新しい。 旧48番館の場合は、長い間倉庫として使われていた建物を解体している最中に、煉瓦積みの壁が発見され、1883(明治16)年頃に創建された現存最古の煉瓦造建造物であることが判明した。修理工事を経た現在では、指摘されなければとても明治時代の建築とは分からない外観となっているが(図1)、内部をのぞいてみれば煉瓦積みの壁があらわになっており、横浜では珍しいフランス積みの煉瓦壁が確認できる。 一方、旧91番地の塀は、同地でのマンション建設工事に際して発見されたものである。調査の結果、石積みの腰壁部分の上に煉瓦積みの壁が立ち上がる構造であることが確認され、現地では、その構造が分かるように表面のモルタルを一部剥ぎ取って保存されている(図2)。 旧48番館は神奈川県の指定文化財として、旧91番地塀は横浜市の地域有形文化財として、いずれも文化財指定を受けて保存される運びとなった。しかし、対象が地下遺構となると、なかなか保存のための対策がたてにくい。91番地の場合、敷地内を掘削した際に、広い範囲で煉瓦構造物が確認されたようであるが、残念ながら、それらの記録は残っていない。 |
|||||||||||||||||||||
|
地中に眠る都市の記憶 しかし実際には、こうした地下遺構の発見事例は頻繁に報告されている。 たとえば2004(平成16)年2月、山下町51番地での建設工事に際して、煉瓦造の基礎構造物が発見された。工事現場が当館の目と鼻の先にあった関係で、筆者は偶然にも、遺構発見当日に現場を見せてもらうことができた(図3)。 震災直前に同地に建っていたのは、「日英館」と呼ばれていた外資系銀行の建物である。建物に関する情報はわずかしかなかったが、震災後に煉瓦造の建造物が建てられたとは考えにくいため、発見された遺構は「日英館」の建物基礎と判断された。 工事が進行している関係上、当館では出土した煉瓦の一部を採集するにとどまったが、その後、施主である読売新聞社がこの発見に大きな関心を持ち、出土した大量の煉瓦は、竣工した新オフィス(読売横浜ビル)1階ホールのディスプレイとして利用されることとなった。 展示されている煉瓦には、”SHINAGAWA“と刻印された品川白煉瓦株式会社製の耐火煉瓦、そして桜マークの刻印をもつ東京・小菅集治監製の赤煉瓦が含まれている。日英館の竣工は1909(明治42)年頃と思われるが、当時横浜の建設現場では、どのようなルートで煉瓦が供給されたのか、展示されている煉瓦はそのひとつの手がかりとなる。 |
|||||||||||||||||||||
|
地中に眠る都市の記憶 そして、今回の企画展示「地中に眠る都市の記憶」(企画展示案内参照)の準備中にも、地下遺構発見の知らせが入ってきた。場所は中華街の南門通りに面した山下町136番地で、「横浜媽祖廟(まそびょう)」の建設工事が進められていた。隣接する135番地は、旧清国領事館所在地で、現在は山下町公園として整備されているが、この公園整備の際にも清国領事館に関係すると思われる遺物が採集されている。 現場では、煉瓦を2枚ずつ縦横に組み合わせて敷き詰めた面が検出された(図4)。敷地の断面を見ると、煉瓦を含む大量の瓦礫(がれき)を埋めた上に、1枚厚の煉瓦面が広がっており(図5)、また瓦礫と煉瓦面との間には焼けた土の層が確認できたことから、煉瓦面は震災後のものと判断された。敷き詰められた煉瓦は、モルタルなどを使用せずじかに組み合わされており、中庭あるいは土間のような形式であったと思われる。 震災前の同地に建っていたのは、レストランやバーなどの店舗が入った雑居ビルであり、当時の広告から煉瓦造の建物であったことがわかる(図6)。地中の瓦礫には、おそらくこの建物のものも含まれているであろう。現場で採集した煉瓦からは、明治時代の早い段階から生産されている手抜き成型の煉瓦と、明治後半になって普及する機械成型の煉瓦の二種類が確認され、手抜き成型のものからは分銅型の刻印が見つかった。そのほかの出土遺物として、ジェラール製の有孔煉瓦や熱で溶けたガラス瓶などを採集した(図7)。 現地では、施主である横浜媽祖廟のご理解もあって、幾度か現場確認をする機会を設けていただいたうえ、出土した煉瓦を今回の展示で活用させていただくことになった。また現在建設中の媽祖廟でも、これらの煉瓦を施設の一部に再利用するという。中華街の歴史を遺構・遺物の面からも大事にしたいとする施主の判断の結果である。 近代遺跡という視点 上記のような報告は、今後もますます増えていくと思われる。とくに山下町・山手町といった旧居留地では、大規模な高層建築が建てられていなければ、こうした震災前の煉瓦構造物が今なお地中に眠っていることは十分に考えられる。むろん、発見された地下遺構のすべてを保存することなど現実には不可能であるが、そこで得られる知見を一つずつ積み重ねていくことで、失われた明治・大正の都市の実像がよりリアルに私たちの目の前に現れるはずである。 近代の埋蔵物が、縄文時代の遺跡のように埋蔵文化財として扱われていない現在、そうした「近代遺跡」とも呼べる情報については、いまだ十分な蓄積がない。本展示がその基礎となれば幸いである。 |
|||||||||||||||||||||
| (青木祐介) |
||||||||||||||||||||||
日本を愛した建築家J.H.モーガン |
||||||||||||||||||||||
| 関東学院大学人間環境学部人間環境デザイン学科教授 水沼淑子 |
||||||||||||||||||||||
|
ハマの建築家 J・H・モーガン 開国以来、多くの外国人建築家が日本を訪れ各地に足跡を刻んだ。横浜と縁の深い外国人建築家は数多くいるが、関東大震災後の横浜で活躍した外国人建築家といえば、J・H・モーガンだろう。 モーガンは1920(大正9)年、アメリカの建設会社フラー社の設計技師長として来日した。シカゴやニューヨークの高層ビルの建設で頭角を著したフラー社は、第一次世界大戦後の日本にアメリカ式の近代的施工方法を伝授すべく招聘(しょうへい)され、丸ビルや日本郵船ビルなどを手がけた。フラー社は日本進出に際しアメリカから建築家を連れてきた。日本で仕事を展開するためには自前の建築家が必要と判断したのだろう。それが、モーガンである。丸ビル建設に際してのモーガンの役回りは施工に関わる図面の作成などにあったようだが、1921(大正10)年にフラー社が施工した神戸クレッセントビルや1922(大正11)年の立憲政友会本部はモーガンが設計を担当した。モーガンはこうして日本での建築家としてのスタートを切った。 フラー社は関東大震災後、さまざまな要因で日本から撤退する。しかし、モーガンはそのまま日本に残り、日本で建築家として生きる道を選択した。東京の日本郵船ビルに事務所を構えた後、1926(大正15)年に横浜に移り、1928(昭和3)年には自らが設計した横浜関内のユニオンビルディングを本拠とし、1937(昭和12)年、横浜で逝去するまで旺盛な設計活動を展開した。 |
|||||||||||||||||||||
|
モーガンの経歴 さて、モーガンはいかなる経歴をもつ 建築家だったのだろう。モーガンは1873年、ニューヨーク州バッファロー市に生まれ、ミネアポリスの建築家ダネルのもとで建築の修行をした後、州の建築課、鉄道会社、フラー建築会社などで経験を積み、20世紀初頭にはニューヨークのマディソンアベニューで建築設計事務所を自営した。アメリカでのモーガンの作品には劇場、オフィスビル、集合住宅などさまざまな種類の建築が並ぶ。古典主義に基づく建築がほとんどだが、用途に応じて巧みに変化を付けながら器用に仕上げている。フラー社がモーガンを日本に伴ったのはこうした器用さを買ってのことだったのかも知れない。 モーガンは来日後まもなく、東京ステーションホテルで英語の本を読む一人の女性と出会う。石井たまのさんだ。たまのさんとの出会いこそ、フラー社撤退後もモーガンが日本に留まることになった大きな要因だろう。たまのさんは私生活のパートナーであったのみならず、セクレタリーとしてモーガンの日本での設計活動を補佐した。 |
|||||||||||||||||||||
|
モーガンの作品 モーガンが日本に残した作品は大きく四つに分類できる。一つ目は、横浜の外国人コミュニティーにおけるいわば公的な施設。アメリカ領事館や根岸競馬場(現存)、クライスト・チャーチ(現存)、ジェネラル・ホスピタル、横浜外国人墓地正門(現存)などである。二つ目はミッション系の学校建築。関東学院専門部校舎(現存)、同中等部校舎(現存)、立教大学予科校舎(現存)、東北学院礼拝堂(現存)などである。三つ目は、オフィスビル。ニューヨーク・ナショナル・シティ銀行支店やチャータード銀行支店、香港上海銀行支店などである。そして最後が日本に在住する外国人の住宅である。ラフィン邸(現存・現111番館)、ベーリック邸(現存)、デビン邸などである。 モーガンの作品の年譜を見ると、極めて順調に仕事をしていた様子がわかる。震災復興期で新築の需要が多かったこともあるだろうが、ニューヨークでつい最近まで建築家として腕を振るい、フラー社の主任建築家として来日したという肩書きも利いたのだろう。そして、何よりもモーガンの人柄によるところも大きかったのだろう。逝去の際に雑誌『日本建築士』に掲載された追悼文では、アメリカ人特有の性格のうち良いところだけを備え明朗快活な紳士だったと讃えられている。 モーガンの日本での作風は極めて多彩である。古典主義を用いたり、スパニッシュ様式を用いたり、中世城郭風の意匠を用いるなど持ち前の器用さが遺憾なく発揮されている。 |
|||||||||||||||||||||
|
モーガン写真帖と自邸 今回、モーガンの御遺族から横浜都市発展記念館に写真帖をはじめとするモーガン関係資料が寄贈された。これらの中にはモーガンの表の顔ではなく、私人としての日常を知 る手がかりが多く含まれており極めて興味深い。中でもスナップ写真の背景として、モーガンの藤沢自邸がしばしば登場する点は注目に値する。 藤沢市大鋸(だいぎり)に1931(昭和6)年頃建設されたモーガンの自邸が現存していることが判明したのは1999(平成11)年のことだった。111番館の改修工事を担当していた建築家菅孝能氏が深い緑の中に埋もれていた自邸を発見した。日本で活躍した外国人建築家の自邸として極めて貴重であることは言うまでもない。当時既に整理回収機構の管理下にあり、開発の危機にあった。その後、地元を中心に保存のための活動が展開され、現在日本ナショナルトラストによる募金活動が展開されている。 自邸はオレンジがかった瓦屋根に白いモルタルの外壁をもつスパニッシュスタイルの洋館である。しかし主室である食堂、居間は続き間になっており、床を板床とするもののいわゆる和室の意匠である。すなわち、柱を露出させた真壁で、長押(なげし)や欄間(らんま)を備え、むろん床(とこ)の間も設けられている。広縁もある。外観と内部のアンバランスさ。これこそがこの住宅の持ち味である。写真帖にはモーガンの私生活のさまざまな場面の背景として自邸が登場する。この写真帖から、外観は一部の増築を除いてほぼ当初のままであることが確認できる。また、モーガンがどのような生活をしていたのかを知る手がかりにもなる。 |
|||||||||||||||||||||
| 写真帖などに残されたモーガン夫妻の日常生活の痕跡には、モーガンがなぜ日本に来たのか、なぜ日本に残ったのか、なぜ不可思議な自邸を造ったのか、などなどモーガンをめぐる謎を解き明かす鍵が隠されているように思われるのである。 |
||||||||||||||||||||||
|
−常設展示より− 横浜と野球(ベースボール) ここに紹介した写真は、当館常設展示「ヨコハマ文化」ゾーンの「するスポーツ、みるスポーツ」のコーナーにパネルが展示されています。 1934(昭和9)年11月2日、アメリカ・メジャーリーグの選抜チームが横浜港に上陸した。ヤンキースのスーパースター、ベーブ・ルースをはじめ、同じくヤンキースの鉄人ルー・ゲーリッグなど、そうそうたる顔ぶれであった。迎える日本には、まだプロ野球が誕生しておらず、学生野球のOB選手などが集められ、全日本チームが結成された。沢村栄治、スタルヒン、三原修、水原茂、中島治康などがこの中にいた。 日本とアメリカの野球の試合は、第1戦の神宮球場を皮切りに、甲子園球場、名古屋の鳴海球場、静岡の草薙球場のほか、仙台、富山、小倉など全国の各地をめぐって開催された。そのうち第9戦(11月18日)の舞台となったのが横浜である。 横浜の野球の歴史は古く、明治の初期より居留地の外国人が横浜公園で野球を楽しんでいた。やがて横浜商業学校(Y校、現横浜商業高校)などの学生を中心に日本人による野球の試合も行われるようになった。昭和に入ると、1929(昭和4)年に横浜公園野球場が完成。本格的なスタジアムが横浜に誕生した。 日米野球が行われたのはもちろんこの球場である。試合は21対4でアメリカの圧勝。3番ベーブ・ルース、4番ルー・ゲーリッグに連続ホームランが飛び出している。ルースはさらにもう1本、特大のホームランを放った。写真は全米チームのユニフォームを着たルースである。 この年、集められた全日本チームをもとに大日本東京野球倶楽部(東京巨人軍、現読売ジャイアンツ)が創立された。そして、大阪野球倶楽部(大阪タイガース、現阪神タイガース)、名古屋軍(現中日ドラゴンズ)などの球団が続々と結成され、1936(昭和11)年よりリーグ戦が始まっている。日本のプロ野球の誕生で ある。 なお、横浜公園野球場は戦後、ゲーリッグ球場、横浜平和球場と名を変え、半 世紀にわたって市民に親しまれた。1978(昭和53)年、横浜スタジアムとして生まれ変わり、横浜初のプロ球団・横浜大洋ホエールズ(現横浜ベイスターズ)のフランチャイズ球場と なった。 |
|||||||||||||||||||||
| (岡田 直) |
||||||||||||||||||||||
| 参考文献 池井優『白球太平洋を渡る』中公新書(1976年) 小玉順三『横浜と野球 Y校の明治・大正・昭和戦前期野球史』(1987年) 『横浜もののはじめ考』横浜開港資料館(1988年) |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
明治初期の 横浜市街全景写真 −カメラがとらえたまちづくりの胎動− |
||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||
| 昭和初期の横浜市街全景写真 1874(明治7)年頃 鈴木真一撮影・当館所蔵 企画展示「地中に眠る都市の記憶―地下遺構が語る明治・大正期の横浜―」にて一部パネルで紹介しています。 |
||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||
| 横浜市街全景写真:右側 | 横浜の市街は山手と太田の二つの丘に囲まれた平地に発達した。この写真は太田丘陵の突端に位置する伊勢山から市街の全景をとらえたもので、近景の新旧建造物は、そのディテールが手に取るようによくわかる。 右手前( 木立の向こうに霞んで見えるのは、旧吉田新田地域に形成途上の比較的若い市街、その向こうに山手丘陵が見えている。 丘陵突端の手前( 画面中央( |
|||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||
| 横浜市街全景写真:左側 | この写真の圧巻は、なんといっても左手前( 画面左端( 撮影者は画面に書き込まれた漢数字と算用数字の特徴から、横浜を代表する写真家の一人、鈴木真一と考えられる。撮影時期は、ともに1874(明治7)年に竣工した町会所と外務省接客所が写っているので、およそその頃のことと推測がつく。画像はきわめてシャープであり、水平線を始め7枚の写真が寸分の隙もなく接合されている。高度な撮影技術に裏打ちされたパノラマ写真として写真史上の価値も高い。 |
|||||||||||||||||||||
| (斎藤多喜夫) |
||||||||||||||||||||||
| [寄贈資料の紹介] | ||||||||||||||||||||||
| 平成17年1月から8月までに新しく寄贈していただいた資料です。(敬称略)
| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 編集後記 | ||||||||||||||||||||||
| 横浜では「あかいくつバス」という名のレトロ調のバスが走っています。桜木町駅から港の見える丘公園まで、ベイサイドに点在する観光スポットを周遊するバスで、途中の停留所「日本大通り」は当館のすぐそばに設けられています。 今号では市内の各所が話題に上がっています。企画展示「地中に眠る都市の記憶」をご覧になられた後、「あかいくつバス」で市内をまわられてみてはいかがでしょうか。(岡田) | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||